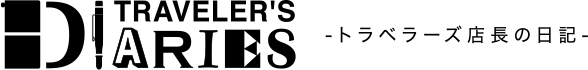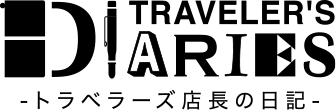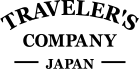I was born in Tokyo.

ほんとうのこと言ってしまうと、僕はあまり東京が好きじゃなかった。
地方出身の友人が、子供時代に野山や川で遊んだ記憶を話されると、ちょっとした劣等感を感じたし、帰るべき故郷があるというのは、羨ましかったりした。できれば自然に囲まれた暮らしに憧れ、森や潮の匂いがすると思い出すような故郷が欲しかった。働くようになって、しばらく仙台に住んでから東京に戻ると、少し狭いアパートが倍の値段。ラッシュの電車や街の人ごみにも今まで以上にストレスを感じるようになって、ますます東京はいやだなあと思ったりした。
でも、最近以前よりも少し東京が好きになったような気がする。例えば、スクラップ&ビルドの流れに逆らい、古き良き東京を再生しようと奮闘している人たちがいる。それは、単なるノスタルジーではなく、サスティナブルで心地よい東京の暮らしを教えてくれる。
人口が多いということは、マイノリティでも、存在感を示すことができるし、ニッチな層に向けたビジネスや手作りのスローな情報発信も質さえ伴っていれば成立するチャンスがある。リーマンショック以降の不景気が地価の低下を招き余計にその流れを助長しているような気がする。
また、海外の人たちの視点が今まで気づかなかった東京の美しさを教えてくれる。ソフィア・コッポラ監督の映画「ロスト・イン・トランスレーション」で描かれた夜の渋谷の風景。台湾の侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の映画「珈琲時光」に映し出される下町の住宅が密集する中を路面電車が走る姿。それらで描かれる東京は、見慣れた風景をどこか異国のような新鮮なものに変えてくれる。
リチャード・ブローティガンが、1976年5月から6月に滞在した東京で、日記を付けるように書かれた詩集「東京日記」も、今まで気付かなかった東京の視点を教えてくれる。新宿の路地にある中華料理店前で寝ている猫。日曜日の夕方の静かな銀座のバーが並ぶ裏通り。夜明け前に塀を乗り越えて忍び込んだ明治神宮。テレビにうつる着物を着た女性。暗い通りを飛ばすタクシー。彼が描く東京は、どれも儚く切なく孤独で、そして美しく、愛にあふれている。目の前に飛んできたハエさえ、愛おしく美しい存在に見えてしまう。
旅する詩人の視点を通して、もう一度東京を眺めると、もっともっと東京が好きになれるような気分になった。