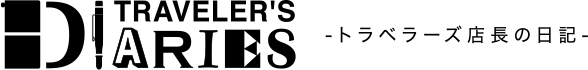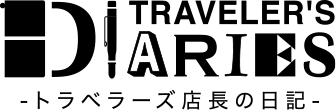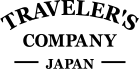京都でのイベント
1982年4月。中学校に入学してはじめて教室に生徒が揃ったときのことだったと思う。先生は簡単に学校の説明をすると、ひとりずつ前に出て自己紹介をしてくださいと言った。もともと人前で話すのは得意でなかった僕は、不安に襲われながら、何を話せばいいのか必死で考え始めた。
そのときは、「あいうえお」順で座っていた。ちなみに、あいうえお順で並ぶと最初になることも多いのだけど、このときは「あ」で始まる苗字の人がいて、僕は2番目だった。
先生は、当たり前のように「あ」で始まる氏名を呼ぶと、自己紹介するように言った。つまり僕はその次ということになる。やばい。僕の心臓は、アクセルを大きく踏み込んだエンジンのように、高速でドクドクと音を立てた。「あ」の生徒は、教室の前に出ると、「XXX小学校から来た〇〇です」と大きな声で言った。そうか出身の小学校を言えばいいのか、なんて思っているとさらに、「得意なことはモノマネです」と言って、当時人気のあった芸人の一発芸をやってのけた。
教室が笑いに包まれた中で、僕の名前が呼ばれた。僕にとっては最悪の空気だ。なんとか「XXX小学校から来たイイジマです」と言葉を発すると、もう頭の中は完全に真っ白。「何が得意だったっけ?」とか、「モノマネできたっけ?」など考えながら、「えー」とか「あー」とかつぶやくように話すのがやっとだった。そんな感じでモジモジしながら、立っていると、そのうち先生は「もう、いいです。席に戻ってください」と冷たく言った。さらに「みんなは自分の番が来る前に何を話すか考えておいてくださいね」と追い討ちをかけるようにつけ加えた。
僕は敗北感に包まれながら席に戻ると、恥ずかしさとか悔しさで頭がいっぱいになって、その後の他の人たちの自己紹介はほとんど頭に入らなかった。そんな感じで始まった中学生活だから、その後は推して知るべし。僕は、ひとり本を読んだり、音楽を聴いたりすることに没頭していった。
1988年4月。僕は大学に入学すると、それまで一人でやっていたギターをバンドとしてやってみたいと思って、音楽系のサークルに入ることにした。入部を申し込むと、「新歓ライブがあるからまずは来てみて」という先輩から誘われ、後日後行ってみた。
ライブは、僕の好きなバンドのコピーバンドも何組か出演して、楽しいものだった。最後のバンドがローリングストーンズの曲を何曲か演奏すると、バンドのボーカルが「Let’s Spend The Night Together」を演るから誰か歌って、と観客に向かって言った。そして、たまたま僕に目があうと「曲、知っている?」と言う。「あ、はい」と返事をすると「じゃあ、きみね」と言って、僕にマイクを渡した。
そのときも、中学生のときに自己紹介くらい頭が真っ白になったんだけど、イントロのフレーズが鳴ると、僕はめちゃくちゃな英語でがなるように歌い始めた。僕は、何かが弾けたように、恥ずかしさも忘れて感情のままに歌った。
あの頃、カラオケはスナックや宴会場にしかない時代だったから、人前で歌をうたうなんて初めての経験だったし、そもそも人前で歌うのはおろか、話すことだって得意ではなかった。だけど、一人ヘッドフォンで聴きながら口ずさむように歌うことはよくあったし、みんなが好きなことに向き合っているあの場の空気が、自分の中の何かを覚醒させてくれたような気がした。うまく歌うとか考えず(そんな余裕はなかったし、実際かなり下手だったはずだ)、ただ感情に従うことで歌うことができたのだと思う。
「Let’s Spend 〜」を歌い終えると、バンドはそのまま、まだデビューまもなかったブルーハーツの「リンダ・リンダ」を演奏した。すると、ステージに観客がなだれ込んで、演奏者も観客も混ざってみんなで歌った。僕は、このときはブルーハーツもこの曲のことも知らなかったけれど、みんなにあわせて「リンダー、リンダー」と声をあげて歌った。
あの体験があって、僕はロックがますます好きになった。人前で演奏したり、歌ったりする楽しさを知ったし、バンドのメンバーと一緒に何かを作り上げる喜びを知った。自分の中で燻っていたものを、外へと表現することを知った。そして、それは確実に今の仕事にもつながっている。今でも人前で話すことは得意ではないけれど、自分が好きなことについてだったら、少しは話せるようになった気がする。
そして、2024年10月。かなり長い前置きになってしまったけれど、先々週、トラベラーズファクトリー京都で開催したアイトール・サライバさんのワークショップで、彼の話を聴きながら、そんなことを思い出した。
この日開催したのは、アイトールさんが持ってきてくれたさまざまな生地を、トラベラーズノート用のコットンケースに、パッチワークのように縫い付けるワークショップ。そこで、アイトールさんが何度も言っていたのは、「自由に感じたままに縫ってください」ということだった。あえて縫い方などのテクニックの話はあまりせず、「間違いもミスもないんです。それはオリジナリティに繋がるし、ぜんぶ正解なんです」と彼は言った。
「こういうのは初めてなんですよね」と言いながら、最初はたどたどしい手つきで縫っていた参加者の方も、次第に真剣に糸を進めている。アイトールさんはみんなの制作途中の作品を見ながら、いいね〜っと何度も言葉をかけていた。
ワークショップの時間が終わると、アイトールさんを囲んで、参加者みんなで作品を手に写真を撮った。それぞれの作品は、同じ生地を使っているのにみんな違う。刺繍の経験がある方も、まったくの初心者も、とても新鮮な体験で楽しかったです、と言っていたのが印象的だった。それぞれの人にとって、ちょっとした覚醒を与えてくれるようなイベントになったら嬉しいな。そんなことを思った。
イベントを終え、あらためてアイトールさんのパッチワークの作品を見ると、とにかく自由で誰の作品にも似ていない。だけど、アイトールさんの作品であることはすぐ分かる。楽しいと寂しい、かわいいと不気味、きれいとボロボロ、シンプルとカオスのように相反する感覚が同居する。おばあちゃんが使っていた古いベッドシーツの切れ端を、自分の家で飼っている羊の毛から紡いだ糸で縫っていたりして、そのすべてに物語が宿っている。
彼の作品を眺めていると、中学生の頃の散々だった自己紹介も、大学生の頃の初ライブ体験も、どちらも同じように自分には意味があることに気づいた。恥ずかしくて忘れたくなるような経験すらも、今の自分を作った大切なこととして、肯定する。そんなことを思い出させてくれる。