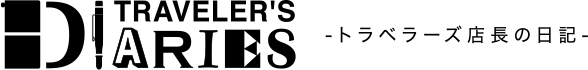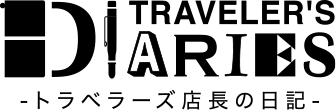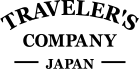バンドマジック

もともと運動や団体行動が苦手だった僕は、チームで一体感を感じながら何かを成し遂げるという経験が乏しかった。はじめて本当の意味でそれを実感できたのは、大学に入学するのと同時にはじめたバンドでの音楽活動だった。
バンドを結成すると、最初はメンバーそれぞれの好きな曲を持ち寄りコピーしていたけれど、1年もするとそれにも飽きて、オリジナルの曲を作って演奏するようになった。メンバーはドラム、ベースにギター2人の4人。ビートルズと同じで、誰が欠けても演奏が成立しにくいロックバンドのスタンダードな構成だった。
ドラム担当は、他のメンバーから比べると頭一つ上回るテクニックを持ちながらも、自己主張が少なく、裏方として支えることに喜びを感じる典型的なドラマータイプ。先輩のバンドと掛け持ちだったことに加え、大学入学後すぐにプリンセス・プリンセスのコピーバンドをしている女の子と付き合いはじめたこともあって、僕らと一緒につるむことが少なかった。ちなみに彼は、その女の子と4年間ずっと付き合い続け、卒業するとすぐに結婚した。
ベース担当は、テクニックはそれほどないけど無理はしないタイプなので、そこそこ安定感のあるベースを弾いた。若い頃の石原裕次郎に似ている少し時代遅れの二枚目ながら、どこか鈍臭いところがあって、それゆえに愛すべきキャラクターでもあった。彼女がいると公言していたのだけど、その彼女はまだ1回しか会ったことがない鳥取に住むペンフレンドで、当時彼が好きなバンドのひとつでもあった爆風スランプの「大きな玉ねぎの下で」を地でいっていた。ちなみに知らない人がいるかもしれないので一応説明しておくと、ペンフレンドとは、手紙の交換だけで連絡を取り合う友達や恋人のことで、携帯電話もメールもなかった頃の風習だ。父親が中古車販売業をしていたこともあって、軽自動車だけどバンドで唯一自分の車を持っていたので、よくみんなで彼の車に乗って、学校があった八王子周辺を目的もなく走ったりしていた。
リードギター担当は、僕と高校時代からの友人で、同じタイミングでギターをはじめたにもかかわらず、当時、速弾きギターで知られたエディ・ヴァンヘイレンを敬愛するヘビメタ好きの彼と、パンクロック好きの僕との練習量の違いなのか、持って生まれた才能の違いなのか、たぶんその両方が理由だと思うけど、目に見えてギターの上達のスピードが違って、すぐに僕の技術を圧倒してしまった。僕と違って、バンドマンのくせに学校の授業はさぼらず、予習復習もするような真面目な性格だったこともギター上達の理由のひとつかもしれない。そんなわけで必然的にリードギターは彼が担当するようになった。また、彼は女性にはすこぶる奥手な性格で4年間の学生生活の中で女性にまつわる話は聞いたことがなかった。
そして、ジョー・ストラマーに憧れていた僕は、音痴のくせにヴォーカルと、あまりうまくないサイドギターを担当した。人前で歌う経験なんて、それまでまったくなかったけれど、バンドでの存在価値を作りたかった僕は必死で声を張り上げて歌った。ちなみに僕は、その4年間で彼女はいたことはあったけど、手痛い失恋も経験した。
時は、80年代末のバブル全盛時代。街ではユーロビートにサザンやユーミンが流れ、トレンディドラマのような生活がリアリティのあるものとしてテレビから垂れ流され、テニスやスキーが大学生活の華だった。そんな時代に、ロックが好きでバンドをやろうなんていうことを考える人は、時代の流れに乗ることができない、劣等感と自尊心が複雑に入り混じったひねくれ者ばかりで、それゆえに自然に仲間意識が生まれ、不思議に心が通じ合えた。
オリジナルの曲を作る時は、まずは僕が部屋でひとりで頭を悩ませながら作った曲の歌詞と、譜面なんて書けないからコードだけをレポート用紙に書き留める。スタジオでそのコピーをメンバーに配って、まずはひとりで弾き語りで演奏する。もう一度演奏すると、ドラムがリズムを刻み、ベースやギターがフレーズを重ねていく。それを何度か繰り返すうちに、だんだんと曲の骨格みたいなものができあがってくる。
次の練習では、ベースラインができていたり、かっこいいギターソロが入ったり、さらにここでリズムパターンを変えようとか、コーラスを入れようとか、新しいアイデアがどんどん加わっていく。まるで鉛筆によるラフスケッチに、輪郭が描かれ、色彩が加わるように音楽が作られていった。僕はその時間が大好きだった。
演奏を重ねていくと、4人のキャラクター、技術やアイデアが、混ざり合って化学反応を起こすことがある。その時、4人はお互いを、一人欠けても成り立たない運命共同体のような存在だと感じ、永遠に続くかのような高揚感とともに唯一無二の圧倒的なグルーブが生まれる。まさにバンドマジックと呼ぶべき体験だった。
それを知ることができたのは、僕にとってとても大きなことで、トラベラーズノートを作る時から今に至るまで仕事で何かを作るということに大きな影響を与えている。僕にとって一緒に何かを作るチームは、バンドのようでありたいし、バンドマジックを体感するように仕事をしたいと思っている。
ここまで書いていたら、久しぶりにあの頃の曲を聴きたくなってきた。それぞれ就職先も決まり、もうすぐ大学生活が終わろうとする頃、宅録好きの友人に頼んで、多重録音機で演奏を録音し、カセットテープに残していた。当時は考えられなかったけど、今ではそれをパソコンに取り込んでCDに焼くこともできるし、iPhoneで聴くこともできる。
あらためて聴いてみると、あの頃の心境の変化みたいなものに気付いたりもする。例えば、当時はまったく意識していなかったけど手痛い失恋の前と後では歌詞のトーンが違い、いつその曲を作ったかは覚えていなくても、その前か後かは今ではよく分かる。それ以前の歌詞は直接的で、どこか前のめりでいきがっているように感じるけど、後では言葉はより抽象的で、悲哀とともにほのかに深みを感じさせるようになった気がする。あの経験が、絶望とともにどんよりした鉛色の雲となって心に暗い影を落としていったのだけど、それは自分の人格や価値観を作ることに少なからず影響を与えていることも分かった。
それとは別に聴いてみて思ったのは、30年前のあの頃と今の自分がびっくりするくらい何も変わっていないということだった。
「雲の隙間から現れては消える
あの光はどこまで続くのか
何度目が覚めても、何も変わってない
自分に気づいてうろたえるだけ」
あれから30年、ギターは埃をかぶって弦もすっかり錆びてしまっているのに、あの頃自分が書いた歌詞に思わず共感してしまうくらい自分は何も変わっていないことに気づいて思わずうろたえてしまった。いったい30年間、僕はどこに向かって旅をしてきたのだろう。あの頃、大人はもっと心に余裕があって、物事に動じることなく、冷静で合理的に判断し行動するものだと思っていた。だけど50歳になっても、パンクロックが好きで、バンド幻想を信じているし、物事に動じやすく心は揺さぶられっぱなしで、相変わらずうろたえてばかり。なんとかしたいと思ってるんだけどね。
話は変わりますが、バンドメンバー募集です。トラベラーズファクトリー 京都の発表とあわせてスタッフの募集も開始しています。興味のある方はこちらをご覧ください。