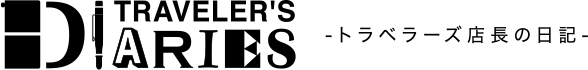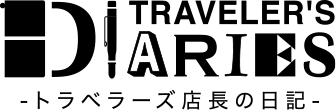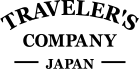カセットテープ・ダイアリーズ

昔、出張でアメリカへ行った時のこと。
カフェでブルース・スプリングスティーンの『Born in the USA』が流れてくると、上司は「この曲、嫌いだよ」と、ちょっと苦い顔をして呟いた。当時、アメリカはブッシュ政権が2期目を迎えた直後。イラク戦争が終わったけれど、その口実だった大量破壊兵器は見つからず、アメリカの強引なやり方に批判が出ていた時だった。アメリカが好きではあるけど、保守派による自国第一主義や差別的な考えには批判的で、リベラル派に共感していた上司にとって、この曲はマッチョで保守的なアメリカを無批判に礼讃している歌だと認識していた。
スプリングスティーン・ファンの僕は、「いや、この曲はアメリカ讃歌ではなくて、ベトナム帰還兵の辛く厳しい現実を語りながら、皮肉的にBorn in the USAと歌っているんですよ」と、薄い知識をもとに誤解を解こうと説明した。だけど「そうなんだ...」と上司は納得したのか、しなかったのかよく分からない、あいまいな返事をして、次の話題へと流れていった。
英語をほぼ完璧に話す上司がそう誤解するのも無理はなく、この曲がリリースされた直後、アメリカの負の現状を哀しみとともに歌う曲なのに、サビの部分だけが強調されて単純なアメリカ万歳の歌として、レーガン大統領の選挙戦でテーマ曲のように使われていたりした。ちなみにスプリングスティーンは民主党支持者で、そのような曲の使われ方を快く思っていなかったと語っている。
そういえばトランプは、選挙運動集会でいつもローリングストーンズの『悪魔を憐む歌』を流していて、ストーンズ側は怒って止めようとしているのだけど、止められないみたいだ。ただ「私は悪魔」だと歌うこの曲にあわせてトランプが登場し、支持者が拍手喝采しているのもどうかと思うけど。
日曜日、都知事選の投票に行って、その後ブルース・スプリングスティーンが題材の映画『カセットテープ・ダイアリーズ』を見に行った。この映画は、イギリスの小さな町で冴えない生活を送っている高校生が、スプリングスティーンの音楽に影響を受けていくことで、ポジティブに変わっていき、成長していくという話で、まさに僕が大好きな音楽青春映画の王道パターン。さらに舞台となっている1987年は、主人公と同じように僕も冴えない高校生でスプリングスティーンに夢中になっていた頃。この映画のことを知ると迷わず観に行こうと決めた。
主人公がスプリングスティーンの音楽とはじめて出会うシーンがすばらしい。主人公は、不況下のイギリスの小さな町ルートンで暮らすパキスタン移民の息子で、それゆえに差別があったり、父親が失業していたりして厳しい生活を強いられている。女の子にもてなくて、詩や文章を書くのが好きだけどそれにも自信が持てなくなっている。そんな中、入学したばかりの高校で、ふとしたきっかけで、同級生からスプリングスティーンのカセットテープを渡される。
夜、部屋でカセットをウォークマンにセットすると『Dancing in the dark』が流れる。その瞬間、主人公は心に稲妻が落ちたような強い衝撃を受ける。このシーンでは、リリックビデオみたいに映像に歌詞が現れてその意味を伝えてくれるのだけど、字幕を目で追いながら『Dancing in the dark』を聴いていると、僕も胸がどんどん熱くなり瞼がウルウルしてきた。
「そうか、こんな歌詞だったんだ」明るくポップな曲調に隠されたその曲の真意をはじめて知って、またあらためてその音楽にノックアウトされたような気分になった。
この映画は、英国ルートン出身のパキスタン系ジャーナリストの自叙伝が原作になっている。ルートンという聞いたことのない町で、彼がスプリングスティーンの音楽に心を震わせていたのと同じ頃、東京の下町で僕も同じように疎外感や孤独を感じながら、同じ音楽に夢中になっていたんだな。英語圏で暮らす彼とは違って、その歌の意味の半分も理解できていなかったのにね。そんなわけで、いろいろな意味で感慨深い映画でした。
ブルース・スプリングスティーンは、常に社会の底辺で這いつくばって苦悩している人たちの叫びを歌にして、時代や国境を超えて社会に怒りや疎外感を持つ人たちの心を震わせてきた。都知事選の結果を知って失望している僕は、まだスプリングスティーンの音楽が必要なのかもしれないな。